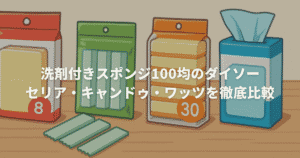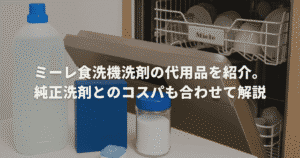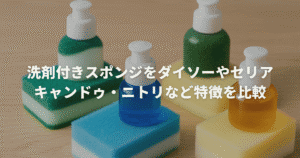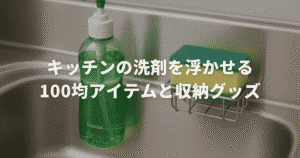鉄フライパンは洗剤で洗ってもいいの?実はためしてガッテンで紹介されたプロの洗い方は、私たちの常識を覆すものでした。
もしかしたら、これまで信じてきた「育てる」というお手入れは、ただの迷信かもしれません。うっかり洗剤で洗ってしまったけれど、本当に大丈夫なのか不安になりますよね。
そもそも何で洗えばいいのか、正しい洗い方が分からない方も多いでしょう。フライパンの側面に付着した茶色いベタベタや、忘れがちな裏側の手入れ、さらにはゴキブリが出るのはなぜ?といった衛生面の悩みまで、鉄フライパンに関する疑問は尽きません。
銅たわしでこするとどうなるのか、頑固な汚れは再生業者に頼むべきかなど、様々な情報が飛び交い、何が本当で何が嘘なのか混乱してしまいます。この記事では、それらの疑問に全てお答えします。
- ためしてガッテンで紹介された洗剤使用の真実
- 鉄フライパンの正しい洗い方と日々のお手入れ方法
- 焦げ付きやサビなど、よくあるトラブルの具体的な解決策
- 「育てる」という考え方の誤解とフライパンとの上手な付き合い方
汚れが落ちるおすすめの掃除用洗剤はこれ!
本当に汚れが落ちる洗剤ってどれなの?
王道の洗剤からコアな洗剤まで、40種類の洗剤を紹介!
\ 最適な一本が見つかる! /
鉄フライパンと洗剤、ためしてガッテンで分かった事実
- 鉄フライパンは洗剤で洗ってもいい?
- 間違えて洗剤で洗ってしまった時の対処法
- 基本的な洗い方と何で洗えばいいか
- 「洗剤NGは嘘?」という疑問の答え
- フライパンを「育てる」は迷信なのか
鉄フライパンは洗剤で洗ってもいい?

結論から言うと、鉄フライパンは汚れがひどい場合に限り、洗剤で洗っても問題ありません。
「鉄フライパンは洗剤NG」というのが長年の常識でしたが、NHKの人気番組「ためしてガッテン」では、プロの中華料理人が調理後に洗剤を使ってフライパンを洗っている様子が紹介されました。これには驚かれた方も多いのではないでしょうか。
プロのフライパンが洗剤に耐えられる理由は、高温調理によって表面に形成される強固な「重合した油膜」にあります。この油膜は、単に油を塗っただけの状態とは異なり、油の分子が結合してプラスチックのように変化したものです。この膜がコーティングの役割を果たすため、洗剤で軽く洗った程度では簡単には剥がれないのです。
家庭で洗剤を使う際の注意点
家庭用のコンロはプロの厨房に比べて火力が弱いため、同様の強固な油膜が作りにくい場合があります。そのため、日常的な軽い汚れであれば、お湯とたわしで洗うのが基本です。洗剤を使うのは、ソースや調味料がこびりついた時など、お湯だけでは落としきれない頑固な汚れがある場合に留めましょう。そして、洗剤を使用した後は、必ず後述する「油ならし」を行い、油膜を回復させることが重要です。
このように、鉄フライパンは絶対に洗剤で洗ってはいけない、というわけではありません。フライパンの状態と汚れの度合いに応じて、適切に使い分けることが大切です。
間違えて洗剤で洗ってしまった時の対処法
ご家族が良かれと思って洗剤で洗ってしまったり、うっかり自分で使ってしまったりすることもありますよね。でも、一度洗剤で洗ったからといって、フライパンがダメになるわけではないので安心してください。
重要なのは、その後のケアです。洗剤によって表面の油膜がリセットされてしまった状態なので、そのまま使うと焦げ付きやサビの原因になります。そこで必要になるのが「油ならし(シーズニング)」です。
この作業を行うことで、再びフライパンの表面に油膜を作り、焦げ付きにくい状態に戻すことができます。
洗剤で洗った後の「油ならし」簡単ステップ
- フライパンを中火にかけ、水分を完全に飛ばします。
- 火を止め、少し多めの油(1/2カップ程度)をフライパンに入れます。
- 再び弱火にかけ、3分ほどゆっくりと加熱し、油をフライパン全体に馴染ませます。
- 火を止め、油をオイルポットなどに戻します。
- キッチンペーパーを使い、フライパンの内側に残った油を刷り込むように、まんべんなく拭き上げれば完了です。
※作業中はフライパンが熱くなっているので、ヤケドには十分注意してください。
この一手間を加えるだけで、フライパンは元の使いやすい状態に復活します。焦らず、丁寧にお手入れしてあげましょう。
基本的な洗い方と何で洗えばいいか

鉄フライパンの日常的なお手入れは、実はとてもシンプルです。基本は、「調理後、フライパンが温かいうちに、お湯とたわしで洗う」ことです。
この方法が推奨される理由は、育った油膜を落としすぎずに、調理で付着した汚れだけを効率的に除去できるからです。
「洗剤を使わないなんて、衛生的に大丈夫?」と心配になるかもしれませんね。でも、ご安心ください。洗い終わった後にしっかりと火にかけて水分を飛ばすことで、殺菌効果が期待できます。正しい手順を踏めば、衛生面の問題はありません。
何を使って洗うのがベスト?
洗う道具としては、主に以下のものが使われます。
- 亀の子たわし・パームたわし:最も一般的な選択肢です。適度な硬さの繊維が、こびりついた食材カスをしっかりとかき出してくれます。
- ささら:竹を細かく割いて束ねたもので、中華鍋の洗浄によく使われます。熱い状態のフライパンも安全に洗えるのが特徴です。
- スチールたわし(金たわし):頑固な焦げ付きには効果的ですが、研磨力が非常に強いため、せっかく育った油膜や、フライパンの酸化被膜まで削り落としてしまう可能性があります。使用は最終手段と考え、使う際も優しくこするようにしましょう。
洗い方の手順
- 調理後、料理を皿に移したら、フライパンが熱いうちにお湯を流しながら、たわし等で汚れをこすり落とします。
- 洗い終わったら、布巾で水気を拭き取ります。
- コンロで中火にかけ、残った水分を完全に蒸発させます。(これを「空焼き」といいます)
- 火を止め、フライパンが熱いうちにキッチンペーパーなどで食用油を内側に薄く塗り広げ、保管します。
この一連の流れを習慣にすることが、フライパンを長持ちさせる秘訣です。
「洗剤NGは嘘?」という疑問の答え
この疑問に対する答えは、「半分本当で、半分は嘘(状況による)」と言えます。
前述の通り、「ためしてガッテン」でプロが洗剤を使っているのは事実です。これは、プロの厨房の強力な火力と毎日の高温調理によって、家庭では形成されにくい、非常に強固な「重合した油膜」ができあがっているからです。この特殊なコーティングがあるからこそ、洗剤で洗ってもびくともしないのです。
油脂の重合とは?
油は高温で加熱され続けると、分子同士が手をつなぐように結合し、粘り気の強い別の物質に変化します。これが「重合」です。長期間掃除していない換気扇のベタベタ汚れを想像していただくと分かりやすいかもしれません。あれが、まさに重合した油です。鉄フライパンの表面でこれが起こると、非常に強力な保護膜となるのです。
一方で、一般的な家庭の火力や使用頻度では、プロと同じレベルの油膜を維持するのは簡単ではありません。そのため、油膜がまだ十分に育っていない初期段階や、日々の通常のお手入れで毎回洗剤を使ってしまうと、油膜が剥がれてしまい、焦げ付きやサビの原因になりかねません。
これらの理由から、
- 「洗剤NG」は、家庭で鉄フライパンを育てる上でのセオリーとしては正しい(本当)。
- しかし、フライパンが十分に育ち、強固な油膜が形成されれば、洗剤で洗っても大丈夫になる(嘘)。
という結論になります。自分のフライパンの状態を見極めながら、お手入れ方法を調整していくのが理想的です。
フライパンを「育てる」は迷信なのか
「鉄フライパンを育てる」という言葉はよく聞かれますが、これには一部で「迷信だ」「無意味だ」という意見も存在します。この考え方の違いは、「育てる」という言葉の解釈の違いから生じているようです。
「育てるのは迷信」派の主張
この意見の根拠は、主に以下の2点です。
- 黒い層はただの焦げカス:意図的に油を焼き付けて黒くコーティングするのは、単に酸化した油の焦げカスを付着させているだけで不衛生。いずれ剥がれて料理に混入する。
- くっつかないのは技術の問題:フライパンの状態に関わらず、「調理前の十分な予熱」と「油返し」という手順を正しく行えば、新品の鉄フライパンでも食材はくっつかない。
つまり、特別なコーティングに頼るのではなく、毎回の調理技術こそが重要だという考え方です。
「育てるのは重要」派の主張
一方、従来からの考え方です。
油馴染みの向上:使い込むことで鉄の表面にある微細な凹凸に油が浸透し、馴染んでいく。これにより、油膜が定着しやすくなり、結果として焦げ付きにくい「育った」状態になる。
油を何度も塗り重ねて、意図的に真っ黒で分厚い層を作るような行為は避けるべきです。これは前述の通り、ただの焦げ付きであり、剥がれや衛生面の問題を引き起こす可能性があります。
結論としての「育てる」
これらの意見を総合すると、「育てる」という行為は、「意図的に黒い膜を作ること」ではなく、「正しい使い方と手入れを繰り返すことで、自然と油が馴染み、フライパンが使いやすい状態に変化していく過程」と捉えるのが最も適切でしょう。迷信というよりは、言葉のイメージが少し誤解されているのかもしれませんね。
鉄フライパンのトラブル解決!ためしてガッテン流手入れ
- 側面の茶色いベタベタ汚れの原因と対策
- 忘れがちなフライパン裏側の手入れ方法
- 油が原因?ゴキブリが出るのはなぜ?
- 銅たわしでこするとどうなる?注意点
- 焦げ付いても大丈夫?再生は業者に依頼
- 鉄フライパンと洗剤問題、ためしてガッテンの総まとめ
側面の茶色いベタベタ汚れの原因と対策

フライパンの側面やフチに付着する、茶色く粘り気のあるベタベタした汚れ。これは、調理中に飛び散った油や、油ならしの際に塗り広げた油が、十分に加熱されずに中途半端な状態で酸化し、固まってしまったものです。
調理面ほど高温にならない側面は、油が焼き切られずに残りやすいのです。これを放置すると、見た目が悪いだけでなく、衛生上も好ましくありません。次に使う際にこの汚れが加熱されると、嫌な臭いの原因にもなります。
ベタベタ汚れの落とし方
付着してすぐの軽い汚れであれば、お湯とたわしでこすれば落とせます。しかし、時間が経って固まってしまった頑固な汚れは、少し強力な対策が必要です。
対策方法
スチールたわしや金属製のヘラ(スクレーパー)で物理的に削り落とすのが最も効果的です。フライパンの内側と違い、側面は油膜を気にする必要がないため、洗剤とスチールたわしで力強く磨いても問題ありません。
ただし、フライパン自体を傷つけないよう、力加減には注意してください。少しずつ、根気よくこすり落としていきましょう。
日頃から調理後は側面も意識して洗うことで、頑固なベタベタ汚れの付着を防ぐことができます。
忘れがちなフライパン裏側の手入れ方法
フライパンのお手入れというと、どうしても食材が直接触れる内側ばかりに目が行きがちですが、実は裏側のお手入れも非常に重要です。
裏側を汚れたままにしておくと、様々なデメリットが生じます。
- 焼きムラの原因になる:裏側に付着したススや焦げ付きが断熱材のような役割を果たし、コンロの火の熱が均一に伝わらなくなります。その結果、火の当たりが強い部分と弱い部分ができ、料理に焼きムラが生じてしまいます。
- コンロが汚れる:裏側の汚れが加熱されることで、コンロの五徳に汚れが付着しやすくなります。
「裏側まで手入れするのは面倒…」と感じるかもしれませんが、この一手間が料理の仕上がりを左右するんです。一流レストランの厨房に吊るされている鍋やフライパンは、裏側までピカピカに磨き上げられています。これは、常に最高の状態で調理を行うためのプロのこだわりなのです。
裏側のお手入れ方法
裏側の手入れは、側面のベタベタ汚れと同様に、スチールたわしと洗剤を使ってしっかりと磨き上げるのが基本です。五徳と擦れて黒くなった部分や、吹きこぼれによる焦げ付きなどを、根気よくこすり落としましょう。定期的にこの手入れを行うことで、常に最適な熱伝導を保つことができます。
油が原因?ゴキブリが出るのはなぜ?
「鉄フライパンを使い始めたらゴキブリが出るようになった」という話を聞くことがあります。これは非常に残念なことですが、原因はフライパンの手入れ方法にある可能性が高いです。
ゴキブリは、人間の食べ物だけでなく、特に油を好みます。鉄フライパンのお手入れで使う油が、彼らにとって格好の餌となってしまうのです。
ゴキブリを寄せ付ける原因
- 酸化した油汚れの放置:前述した、フライパンの側面や裏側に付着した茶色いベタベタ汚れは、ゴキブリにとってご馳走です。洗い残しは絶対に避けましょう。
- 保管時の油の塗りすぎ:サビ防止のために塗る油が多すぎると、それが餌になります。保管時の油は、キッチンペーパーで「塗る」というよりは「拭く」くらいの感覚で、ごく薄く均一に伸ばすのがポイントです。触ってみて、ベタつかずサラッとしている状態が理想です。
衛生的な保管を心がけましょう
調理後はなるべく早く洗い、汚れを残さないことが最も重要です。また、長期間使わない場合は、新聞紙などに包んで湿気の少ない場所に保管すると良いでしょう。正しいお手入れは、美味しい料理のためだけでなく、衛生的なキッチン環境を保つためにも不可欠です。
銅たわしでこするとどうなる?注意点

たわしには様々な素材がありますが、その中の一つに「銅たわし」があります。銅は抗菌作用があることや、その独特の見た目から選ばれることがあります。
鉄フライパンの洗浄に銅たわしを使用した場合、汚れ落としの効果は期待できますが、一つ注意点があります。それは、「色移り」の可能性です。
銅は鉄よりも柔らかい金属です。そのため、銅製のたわしで鉄製のフライパンを強くこすると、たわしの銅がわずかに削れてフライパンの表面に付着し、ブロンズ色のような色が移ってしまうことがあります。
これは製品の不具合や有害なものではありませんが、見た目が気になる方もいるかもしれません。
色移りの可能性を理解した上で、その特性(抗菌性など)を重視するなら使用しても良いでしょう。もし色移りが気になる場合は、従来通りの亀の子たわしや、より強力な洗浄力が必要な場合はスチールたわしを選ぶのが無難です。
それぞれの道具のメリット・デメリットを知り、ご自身の目的に合ったものを選びましょう。
焦げ付いても大丈夫?再生は業者に依頼
ひどい焦げ付きや、うっかりお手入れを忘れて発生させてしまったサビ。テフロン加工のフライパンなら諦めてしまうような状態でも、鉄フライパンなら再生できるのが最大の魅力です。再生には、自分で行う方法と、専門の業者に依頼する方法があります。
自分で再生する方法
時間はかかりますが、道具があれば家庭でも再生は可能です。料理研究家の樋口直哉氏が紹介している方法が参考になります。
- 焼き切り:屋外など換気の良い場所で、ガスバーナーを使ってフライパン全体の汚れを完全に炭化させます。(家庭用コンロは安全センサーが働き高温にならないため、バーナーが推奨されます)
- 削り落とし:炭化した汚れを、金属製のヘラ(スクレーパー)でガリガリと削り落とします。
- 研磨:目の粗いサンドペーパー(#100程度)から始め、徐々に目の細かいもの(#200程度)に変えながら、表面のサビや残った汚れを磨き落とします。鉄の地金が見えるまで磨くのがポイントです。
- 仕上げ:メラミンスポンジでさらに磨き、水洗いします。
- 空焼きと油ならし:最後に、フライパンを火にかけて青っぽくなるまで焼き(酸化被膜の再形成)、冷ましてから「油ならし」を行えば完了です。
専門業者に依頼する方法
「自分でやるのは大変そう…」という場合は、鍋やフライパンの再加工を専門に行う業者に依頼するのも一つの手です。費用はかかりますが、プロの技術で新品同様の状態に再生してもらえます。
業者によっては、フッ素樹脂(テフロン)の再加工など、様々な加工に対応している場合もあります。愛用のフライパンを長く使いたいけれど、自分でのメンテナンスに自信がない方は、一度相談してみる価値はあるでしょう。
| 再生方法 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 自分で再生 | ・コストが安い ・道具への愛着が深まる | ・手間と時間がかかる ・専門的な道具(ガスバーナー等)が必要な場合がある |
| 業者に依頼 | ・手間がかからない ・プロの仕上がりで確実 | ・費用がかかる ・依頼から完了まで時間がかかる |
鉄フライパンと洗剤問題、ためしてガッテンの総まとめ
この記事では、ためしてガッテンで話題になった鉄フライパンと洗剤の関係から、日々のお手入れ、トラブルシューティングまで幅広く解説しました。最後に、重要なポイントをリストで振り返りましょう。
- 鉄フライパンは基本的に洗剤不要だが、頑固な汚れには使用しても良い
- ためしてガッテンでプロが洗剤を使う理由は強固な「重合した油膜」があるから
- 家庭で洗剤を使った後は必ず「油ならし」で油膜を回復させる
- うっかり洗剤で洗ってしまっても油ならしをすれば大丈夫
- 日常の洗い方はお湯とたわしが基本
- 洗い終わったら必ず火にかけて水分を飛ばしサビを防ぐ
- 「フライパンを育てる」とは正しい手入れで油が馴染んだ状態のこと
- 意図的に黒い焦げ層を作るのは間違い
- 側面の茶色いベタベタは酸化した油汚れで、しっかり落とす必要がある
- 裏側の汚れは熱効率を下げ焼きムラの原因になるため手入れが重要
- 洗い残しの油汚れはゴキブリの原因になるので衛生管理を徹底する
- 銅たわしは汚れを落とすが、鉄に色が移る可能性がある
- ひどい焦げやサビは自分で再生可能であり、専門業者に依頼する選択肢もある
- 鉄フライパンは正しい知識で付き合えば一生ものの調理器具になる
- 状況に応じてお手入れ方法を使い分けることが大切