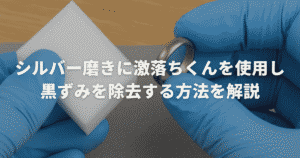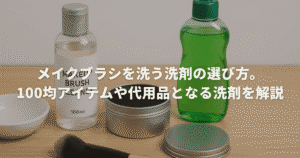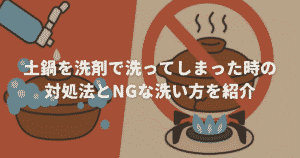金属磨きに定評のあるピカール。しかし中にはコンパウンドとの違いや実際の用途・効果について戸惑いを感じる方も多いのではないでしょうか?
ピカールにはいくつかの種類が存在し、それぞれの特徴を知らないまま使ってしまうと、素材をキズ付けてしまう場合もあります。
また
- ピカールは何番相当なのか?
- 車のボディにも使えるのか?
- 包丁を磨いても問題ないのか?
といった疑問はよくあるものです。またピカールネオとの違いや番手一覧で他のコンパウンドと比較したいという方も多いでしょう。
この記事では、ピカールとピカールネオの違いを中心に、それぞれの用途やメリット・注意点を解説します。さらに、鏡面にならない原因と対処方法など実用的なポイントにも触れながら、ピカールを正しく活用するための知識をお伝えします。
- ピカールとピカールネオの違い
- 使用できる素材や用途の違い
- 番手換算による研磨力の目安
- 鏡面仕上げができない原因と対処方法
ピカールとコンパウンドの違いとは?
- ピカールはコンパウンド?
- ピカールの種類と特徴を解説
- ピカールとピカールネオの違い
- ピカールは何番相当のヤスリ?
- コンパウンド 番手一覧と比較
- 鏡面にならない原因と対処方法
ピカールはコンパウンド?

ピカールは、金属表面の汚れや酸化膜を除去し、光沢を出すために使われる研磨剤ですが、その成分や働きから見て「コンパウンド」としての性質も持ち合わせています。つまり、研磨粒子を含んだ液体状の製品であるため、広い意味ではコンパウンドに分類されます。
ただし、一般的に「コンパウンド」というと、自動車の塗装面を磨くために開発された製品を指すことが多いため、ピカールとは用途や性能に違いがあります。ピカールはあくまで金属研磨用に設計されており、塗装面などには不向きな場合があります。したがって、目的に合った製品選びが重要です。
ピカールの種類と特徴を解説
ピカールシリーズは「液体」「半練り(ネリ)」「クリーム」「スプレー」の4系統に大別され、粒子径・基剤粘度・溶剤の有無で細分化されています。核となる研磨材はいずれも酸化アルミニウム(アルミナ)ですが、平均粒径と分散濃度が異なるため、切削力と仕上がりに階層的な差が生まれます。以下では日常使用で選択肢となりやすい5製品を中心に、処方と用途を詳しく整理します。
第一に「ピカール液」はシリーズの原点であり、灯油系溶剤に平均3µm粒子を約20%分散させたシャバシャバの液体タイプです。真鍮、銅、ステンレスなど幅広い金属のサビ取りやくすみ落としに対応し、磨き込むにつれて粒子が破砕して最終的に2µm前後まで微粒化する自己減耗特性を備えています。ただし強い灯油臭が作業環境を選ぶこと、液だれしやすく細部には塗布量の調整が必要な点がデメリットになります。
次に「ピカールネオ」はピカール液と同じ3µm粒子を用いながら、溶剤を低臭パラフィン系に置き換えた室内向けモデルです。揮発臭が約70%低減し、粘度をわずかに高めて布への含浸量を一定にしやすい処方としたことで、磨きムラや飛散を抑制しました。金属パーツを居室でメンテナンスしたい場合や、換気の難しい冬場にも扱いやすいのが大きな利点です。
三つ目の「ピカールケアー」は3µm粒子を同濃度で配合しつつ、油脂系増粘剤でクリーム状に仕立て、チューブ容器に充填したモデルです。キャップを開けて必要量だけ絞り出せるため、指輪や時計ベゼルなど小面積の部分磨きに最適で、液体より飛び散りにくく保管時の液漏れもありません。硬質ステンレスの鏡面仕上げや最終の光沢出しに向きますが、切削力はピカール液と同等なので深いキズ消しには不向きです。
より荒い研磨が必要な場面では「ピカールネリ」や「ピカールラビングコンパウンド」を使います。ネリは10µm粒子を高濃度で半練り化したペーストで、バフホイールに擦り付けても垂れにくく、アルミホイールの白化や鍛造部品の酸化皮膜を短時間で除去できます。ラビングコンパウンドはさらに粗い15µmシリカ粒子を用い、ペーパー番手で#1000相当の切削力を持つため、鉄ベースのメッキ下地調整や溶接焼けの一次研磨に適しています。
反対に、鏡面を極限まで追い込みたい場合は「ピカールエクストラメタルポリッシュ」が候補になります。平均1µm粒子を油中水滴型で分散し、研磨力というより微細な曇り取りと光沢増強に特化した製品です。プラスチックヘッドライトの最終仕上げや高級カトラリーのメンテナンスで効果を発揮します。
このようにピカールシリーズは“粗磨き→中仕上げ→鏡面”を1ブランド内で循環できる構成になっています。深いスクラッチを消す場合はラビングコンパウンド→ピカールネリ→ピカール液(もしくはネオ)→エクストラメタルポリッシュという4段階を踏むと、ペーパーやバフを併用せずとも均一なミラーフィニッシュに到達しやすくなります。したがって、作業場所の換気性と対象金属の硬度・面積を見極め、臭気許容度と求める仕上がりに応じて各製品を組み合わせることが、失敗しない選択の鍵になります。
ピカールとピカールネオの違い

ピカールとピカールネオは、どちらも日本磨料工業が製造する液状金属研磨剤ですが、開発コンセプトと処方設計に明確な差があります。ピカールは灯油系溶剤に平均粒径約3µmのアルミナ研磨粒子を分散した油中水滴型乳化液で、頑固な酸化膜を素早く除去できる点が特徴です。一方、ピカールネオは低臭パラフィン系溶剤を採用し、同じ粒子径を保ちながら揮発臭を約70%軽減しています。そのため、ネオは室内や集合住宅でも扱いやすく、冬場に窓が開けづらい環境でも作業者への負担が少ないといえます。
研磨力そのものは両製品で大きな違いはなく、紙やすり換算で1000〜1500番程度に相当します。ただしネオは基剤の粘度がやや高めで布への含浸量を一定に保ちやすく、初心者でも磨きムラを抑えて鏡面に近い光沢を引き出しやすい設計です。粗い傷を短時間で削りたい場合や広い金属面を一気に磨きたい場合は、流動性が高いピカールの方が効率的でしょう。
対応素材の観点では、真鍮・銅・ステンレスなど硬質金属のくすみ取りや光沢出しには両製品とも問題なく使用できます。アルミやデリケートなメッキ層の場合は、マイルド処方のピカールネオが安全性の面でやや有利です。逆に、厚い酸化膜が目立つ自転車パーツや工具の再生では、ピカールのストレートな切削力が頼りになります。
作業後の後処理にも違いがあります。ピカールは灯油成分が残りやすいため、仕上げに食器用洗剤やアルコールで脱脂すると変質や再汚染を防げます。ピカールネオは低臭溶剤のおかげで油膜が薄く、水拭きだけでも比較的きれいに仕上がるため、キッチン用品やアクセサリーのように洗浄工程を最小限にしたい場面で重宝します。
コスト面では300g缶のピカールが実売900円前後、180g缶のピカールネオが750円前後と、容量単価はピカールがやや割安です。ただし室内作業の快適性や後処理の手軽さを重視する用途では、ネオに割高分の価値があると言えます。
以上を踏まえると、「強力さとコスト優先ならピカール」「室内環境や素材への優しさを優先するならピカールネオ」という使い分けが基本となります。どちらを選ぶ場合も、塗装面や樹脂面など非金属への誤用を避け、適切な布と研磨手順を守ることで、美しい仕上がりと長期的な素材保護が両立できます。
ピカールは何番相当のヤスリ?
ピカールの研磨力は、紙やすりの番手で表現するとおおよそ1000番から1500番程度に相当すると言われています。これは、目に見えないほどの細かい傷を削り取り、表面をなめらかに仕上げる中程度の研磨力です。
もちろん、実際の研磨効果は素材や使用量、布の種類、力加減などにも影響されますが、金属表面のくすみを取るには十分な性能があります。粗いヤスリで磨いた後の仕上げにも向いており、段階的な作業工程の一部として活用されることが多いです。
そのため、極端に深い傷や厚い酸化膜を除去したい場合には、より粗い番手の研磨剤と併用するのが効果的です。
コンパウンド 番手一覧と比較
金属や塗装面を磨くために使用されるコンパウンドには、さまざまな「番手」が存在します。一般的には、数値が小さいほど粗く、大きいほど仕上げ用となります。例えば、600番以下は塗装前の表面調整、1000番前後は中間仕上げ、2000番以上は最終仕上げや鏡面加工に使われます。
ピカールはこの中で中間仕上げに該当する性能を持つため、番手一覧の中では1000〜1500番相当と理解されることが多いです。ただし、ピカールは液体であるため、ヤスリのような一定の粗さを保つのは難しく、使用環境によって仕上がりに差が出る点は注意が必要です。
他の番手付きコンパウンドと併用することで、より精密な仕上げが可能になります。
鏡面にならない原因と対処方法

ピカールを使っても期待するほど鏡面にならないことがあります。その原因として考えられるのは、使用する布や作業手順の誤り、素材との相性、あるいは研磨不足です。特に柔らかすぎる布や力を入れすぎた作業は、仕上がりを曇らせる要因となります。
また、下地処理が不十分な場合も、表面の細かな凹凸が残ってしまい、光沢が出にくくなります。このため、粗めの研磨剤で下処理をした後にピカールで仕上げると、より美しい鏡面に近づきます。
さらに、ピカールには種類があり、鏡面仕上げに特化した製品(例:ピカールケアー)を選ぶことも重要です。正しい手順と道具を使うことで、満足のいく仕上がりに導くことができます。
ピカールとコンパウンドの使い方と注意点
- なぜダメ?用途別の注意点
- ピカールで包丁を磨いても大丈夫?
- 車のボディに使える?
- 金属ごとのおすすめ使用法
- 使う順番と磨き方のコツ
なぜダメ?用途別の注意点
ピカールは便利な研磨剤ですが、すべての素材や場面で使用できるわけではありません。例えば、塗装された面やコーティングされた金属に使用すると、表面を削ってしまい元の仕上がりを損ねる恐れがあります。
また、プラスチックやアクリルなどの樹脂系素材に対しては、ピカールに含まれる成分が表面を曇らせたり、傷を残す可能性もあるため注意が必要です。特に高価な製品や目立つ場所には、事前に目立たない部分でテストすることが推奨されます。
誤った使用は、素材そのものを傷めるリスクがあるため、製品ラベルやメーカーの使用説明をよく読み、適切な使い方を心がけましょう。
ピカールで包丁を磨いても大丈夫?

ピカールで包丁を磨くことは可能ですが、用途と目的によって使い方を慎重に選ぶ必要があります。主に表面のサビやくすみを落とす程度であれば問題ありませんが、刃そのものに使用するのは避けた方がよいでしょう。
理由は、ピカールに含まれる研磨粒子が刃先の精密な角度を変えてしまい、切れ味を損なう可能性があるからです。また、食品に接する道具であることから、使用後にはしっかり洗浄し、研磨成分が残らないようにすることも重要です。
包丁の光沢を保ちたい場合には、刃以外の部分に限定して使う、あるいは食品対応の研磨剤を使うなど、安全面に十分配慮する必要があります。
車のボディに使える?
ピカールを車のボディに使うことは、基本的には推奨されていません。なぜならば、ピカールの研磨力は金属向けに設計されており、自動車の塗装面には強すぎる可能性があるからです。これにより、塗装が剥がれたり、ムラができたりすることがあります。
ただし、クロームメッキ部分や金属のパーツには使用可能な場合もあります。実際、ホイールやマフラーのサビ取りに使われることもありますが、こちらも事前のテストと注意が必要です。
自動車には専用のコンパウンドが多数販売されているため、そちらを使う方が安全で確実です。車のボディケアでは、素材に応じた製品を選ぶことが、美しい仕上がりへの近道です。
金属ごとのおすすめ使用法
ピカールは、真鍮、銅、ステンレス、アルミなどさまざまな金属に使用できますが、素材によって磨き方や注意点が異なります。
例えば、真鍮や銅は酸化しやすいため、ピカールで定期的に磨くと美しい光沢を保ちやすくなります。ただし、柔らかい素材なので、力を入れすぎると表面を削りすぎることがあります。
ステンレスは比較的硬い金属で、キッチン用品や工具など幅広い製品に使われています。ピカールで磨くことでくすみが取れ、光沢を取り戻すことができます。一方で、アルミはややデリケートな素材であるため、優しく扱い、仕上げに柔らかい布を使うのがポイントです。
素材に応じた磨き方を理解することで、より安全で効果的にピカールを活用できます。
使う順番と磨き方のコツ
ピカールを効果的に使うには、磨く前の準備から丁寧に行うことが重要です。まず、対象物の表面に付着したホコリや油分を取り除いてから作業を始めましょう。
次に、柔らかい布にピカールを少量取り、一定方向にやさしくこするようにして磨きます。このとき、力を入れすぎると傷になるため注意が必要です。また、広い面積を磨く場合は、数回に分けて少しずつ作業を進めるとムラが出にくくなります。
仕上げには、乾いた布でしっかり拭き取り、研磨成分を残さないようにします。必要に応じて、水洗いや中性洗剤での洗浄も行うと清潔に保てます。順を追って丁寧に進めることで、光沢のある美しい仕上がりになります。
ピカールとコンパウンドの違いを総括
以下はこの記事のまとめです。
- ピカールは研磨剤でありコンパウンドの一種といえる
- 一般的なコンパウンドとは用途や性能に違いがある
- ピカールには液体・ペースト・スプレーなどの種類がある
- ピカールネオは臭いが少なく室内作業に適している
- ピカールケアーは鏡面仕上げ向けの微粒子タイプ
- ピカールとピカールネオは成分や使用感が異なる
- 紙やすり換算ではピカールは1000〜1500番程度に相当する
- ピカールは中間仕上げ向けの研磨力を持つ
- 鏡面にならない原因は布や手順、素材との相性にある
- 塗装面やプラスチックには不適切な場合がある
- 包丁の刃には使用を避けた方がよい
- 自動車の塗装面への使用は基本的に推奨されない
- 真鍮や銅にはピカールの使用が適している
- アルミは柔らかいため優しく磨く必要がある
- 作業前にホコリ除去と適切な布の選定が重要