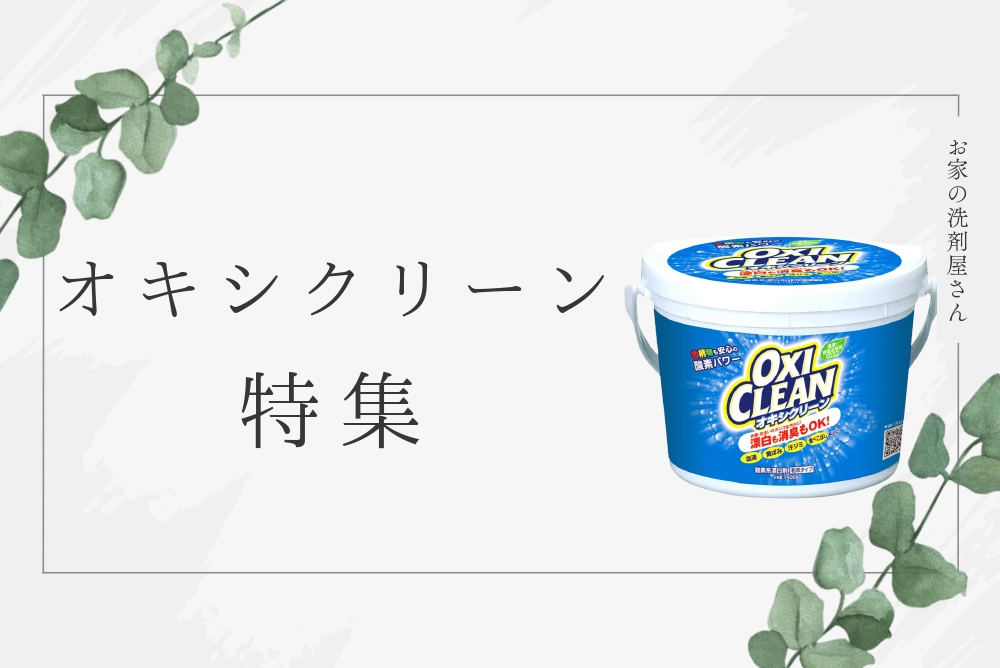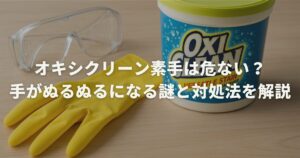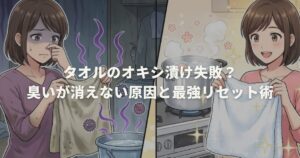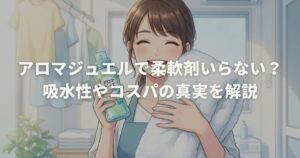お掃除や洗濯で活躍するアイテムとして、オキシクリーンと重曹はどちらも有名ですよね。ただ、この2つ、パッケージは違えど「なんとなく似たようなものかな?」と思って手に取る方も多いかもしれません。白くてサラサラした粉末ですし、どちらも汚れを落とすという点では共通していますからね。
ですが、実際に使ってみると…
- オキシクリーンと重曹の決定的な違いって何?
- 洗濯槽の掃除をしたいけど、結局どっちが正解なの?
- オキシクリーンと重曹を混ぜるのは危険って聞いたけど本当?
- キッチンの油汚れとお風呂のカビ、同じもので掃除していいのかな?
こうした疑問、すごくよく分かります。私も洗剤に興味を持ち始めた頃は、アルカリ性なら大体同じだろうと、この2つの使い分けに何度も悩んだものです。
実は、オキシクリーンと重曹は、得意とする汚れや、汚れを落とすメカニズム(仕組み)が全く異なる、似て非なるアイテムなんです。この違いを知らないまま「なんとなく」で使ってしまうと、期待したほど汚れが落ちない…なんて残念な結果になったり、最悪の場合、大切な素材を傷めてしまったりする原因にもなります。
この記事では、オキシクリーンと重曹、それぞれの本当の実力と、化学的な視点に基づいた正しい使い分けについて、できるだけ分かりやすく、詳しく解説していきますね。この記事を読み終える頃には、あなたの疑問もスッキリ解決しているはずです!
- オキシクリーンと重曹の「洗浄力の源」である化学的な違い
- 汚れの種類(油汚れ・焦げ・カビ・水垢)に合わせた「どっちが正解か」の選び方
- 混ぜてもOK?安全な「オキシペースト」の作り方と具体的な活用法
- 洗濯槽やキッチン、お風呂掃除でのシーン別・具体的な使い分けガイド
汚れが落ちるおすすめの掃除用洗剤はこれ!
本当に汚れが落ちる洗剤ってどれなの?
王道の洗剤からコアな洗剤まで、40種類の洗剤を紹介!
\ 最適な一本が見つかる! /
オキシクリーンと重曹の基本的な違い

まずは、「オキシクリーンと重曹って、根本的に何が違うの?」という一番の核心部分から見ていきましょう。この2つを同じ「アルカリ性の粉末」というカテゴリだけで捉えていると、その本質的な違いを見落としてしまうかもしれません。なぜ洗浄力が違うのか、その「理由」を深掘りしますね。
結局どっち?オキシクリーンと重曹
結論から言うと、この2つは洗浄剤としてのカテゴリーが全くの別物です。
一番の違いは「アルカリ性の強さ(pH)」と、汚れへの攻撃方法である「洗浄メカニズム」ですね。
pH(アルカリ性の強さ)が全く違う
まず、水に溶かしたときの液性(pH)を見てみましょう。中性がpH 7です。
- 重曹(化学名:炭酸水素ナトリウム):pH 8(弱アルカリ性)
- オキシクリーン(主成分:過炭酸ナトリウム):pH 11(アルカリ性)
「pH 8と11か、まあまあ違うな」くらいに感じたかもしれませんが、ここが重要なポイントです。pHの尺度は「対数」といって、数値が1違うと強さが10倍変わります。
つまり、pHが3違うオキシクリーン(pH 11)は、重曹(pH 8)の… 10(pH 9) × 10(pH 10) × 10(pH 11) = 約1,000倍もアルカリ性が強いことになります。
重曹とオキシクリーンは、洗浄パワーが「1,000倍」も違うと聞くと、全く別物であることがイメージしやすいかなと思います。この強さの違いが、得意な汚れの違いに直結しています。
汚れへのアプローチ(洗浄メカニズム)が違う
さらに決定的なのが、汚れへのアプローチ方法です。パワーが違うだけでなく、持っている「武器」が異なります。
洗浄メカニズムの決定的な違い
オキシクリーン(化学的アプローチ) お湯(40℃~60℃)に溶けると化学反応が起こり、「活性酸素」の泡を大量に発生させます。この酸素の力で汚れを化学的に酸化・分解・漂白するのが得意です。純粋な化学的洗浄であり、研磨作用は一切ありません。 (得意技:漂白・除菌・分解)
重曹(物理的・化学的アプローチ) 重曹は2つの武器を持っています。
- 研磨作用(物理的):水に溶けにくい微細な粒子が、クレンザー(研磨剤)として機能し、汚れを物理的に削り落とします。
- 中和作用(化学的):弱アルカリ性(pH 8)で、軽い油汚れや皮脂汚れといった「酸性」の汚れを中和し、水に溶けやすくします。
(得意技:研磨・中和)
つまり、オキシクリーンは「酸素系漂白剤」であり、化学の力で汚れを元から分解するのが得意。一方、重曹は「研磨剤」であり、物理的な力でこすり落とすのが最大の強み、と言えますね。
汚れの種類で見る使い分け
「漂白・分解(化学)」と「研磨(物理)」という得意技が分かれば、シーン別の使い分けはとても簡単になります。
「この汚れは分解すべきか?削り取るべきか?」と考えると分かりやすいですよ。
| 汚れの種類 | 推奨 | 理由(アプローチ) |
|---|---|---|
| 食器の茶渋、コーヒー渋 | オキシクリーン | 色素沈着汚れです。研磨では落ちにくく、酸素による「漂白・分解」が必須です。 |
| 布巾や衣類の黄ばみ・シミ | オキシクリーン | 皮脂汚れや色素沈着が原因。強アルカリと酸素の力で「分解・漂白」します。 |
| 洗濯槽や排水溝のカビ・ぬめり | オキシクリーン | 有機的な汚れ(皮脂・カビ)です。強力なアルカリと発泡力で「剥離・除菌」します。 |
| 鍋・五徳の頑固な焦げ付き | 重曹 | 炭化した硬い汚れです。化学分解より、粒子の力で「研磨(削り取る)」方が効率的です。 |
| シンクの水垢(軽いもの) | 重曹 | 軽い水垢(ミネラル汚れ)は、重曹の「研磨力」でこすり落とすことができます。 |
| 冷蔵庫・レンジ内の拭き掃除 | 重曹 | 食品を扱う場所には、安全性の高い重曹が適任。軽い油汚れを「中和」します。 |
このように、「色素を落としたい」「カビを分解したい」ならオキシクリーン、「焦げを削り落としたい」なら重曹、と覚えておくと、掃除での失敗がぐっと減りますね。
セスキやクエン酸との比較
オキシクリーンや重曹を調べていると、必ずと言っていいほど「セスキ炭酸ソーダ」や「クエン酸」も候補に上がってきますよね。これらとの違いもここでハッキリ整理しておきましょう。
まず、セスキ炭酸ソーダは、重曹とオキシクリーンの中間に位置する「アルカリ剤」です。私は「アルカリ三兄弟」と呼んでいます。
アルカリ三兄弟の使い分け(まとめ表)
アルカリ性の強さは「重曹 < セスキ < オキシクリーン」の順です。
| 重曹 | セスキ炭酸ソーダ | オキシクリーン | |
|---|---|---|---|
| pH(強さ) | pH 8(最弱) | pH 9(中間) | pH 11(最強) |
| 研磨力 | あり(最大の強み) | なし | なし |
| 漂白力 | なし | なし | あり(最大の強み) |
| 水への溶けやすさ | 溶けにくい | 非常に溶けやすい | 溶ける(要:湯) |
| 得意な掃除法 | こする(研磨) | 拭く(スプレー) | 漬ける(漂白) |
この表の通り、セスキ炭酸ソーダは「研磨力も漂白力もない」代わりに、「水に非常に溶けやすく、重曹よりアルカリ性が強い(pH 9)」という特徴があります。この特性が、スプレーボトルでの拭き掃除に最適なんです。
重曹は水に溶けにくいのでスプレーには不向きですが、セスキならサッと溶けて強力なアルカリスプレーが作れます。コンロ周りの軽い油汚れや、ドアノブの手垢汚れを「拭く」のに大活躍しますよ。
役割分担としては、「こする掃除(研磨)」なら重曹、「拭く掃除(スプレー)」ならセスキ炭酸ソーダ、「漬ける掃除(漂白)」ならオキシクリーン、というのが、私のおすすめする使い分けです。
酸性の「クエン酸」の役割
一方、クエン酸はこれら3つとは全くカテゴリが違い、真逆の「酸性」です。
お風呂の鏡や蛇口に付着する、白くてウロコ状のガチガチな汚れ、あれは「水垢(炭酸カルシウムなど)」というアルカリ性の汚れです。アルカリ性の汚れに、アルカリ性のオキシクリーンや重曹を当てても、中和できず全く効果がありません。
こういう時こそ、「酸性」のクエン酸の出番です。酸の力でアルカリ性の水垢を中和し、柔らかくして落としやすくしてくれます。
「キッチンの油汚れ(酸性)にはアルカリ性の洗剤」「お風呂の水垢(アルカリ性)には酸性の洗剤」と、汚れの性質に合わせて使い分けるのが基本ですね。
オキシクリーンと重曹を混ぜる危険性

「混ぜるな危険」という表示を見ると、洗剤同士を混ぜることに強い不安を感じるかもしれません。
まず、最も重要なこととして、オキシクリーン(酸素系漂白剤)と重曹(弱アルカリ剤)を混ぜても、有毒な塩素ガスが発生することはありません。
いわゆる「混ぜるな危険」とは、主に「塩素系漂白剤(カビキラーなど)」と「酸性洗剤(クエン酸、お酢、トイレ用洗剤など)」を混ぜた場合に発生する、有毒な塩素ガスのことを指します。これは本当に危険なので絶対にNGです。
では、オキシクリーンと重曹を混ぜても安全なら、混ぜた方がパワーアップするのでは?と思うかもしれませんが、単純に水に溶かして混ぜただけでは、あまり意味がありません。むしろ、オキシクリーンの強力なアルカリ性(pH 11)が、重曹(pH 8)によって少し弱まってしまう(中和されてしまう)可能性も考えられます。
しかし、この2つをあえて「混ぜる」ことに大きな意味がある、唯一のテクニックが存在します。それが次にご紹介する「オキシペースト」です。
安全なオキシペーストの作り方
オキシペーストは、オキシクリーンと重曹、それぞれの利点を組み合わせた、まさに「ハイブリッド洗浄剤」と呼べるテクニックです。
オキシペーストの作り方(目安)
- 清潔な容器(金属製は避ける)に、オキシクリーンと重曹を「1:1」の割合で入れます。(例:各大さじ1杯ずつ)
- そこに40℃~60℃のお湯を少量ずつ(例:大さじ1杯程度)加えます。※必ずオキシクリーンが活性化する温度のお湯を使ってください。
- ペースト状(歯磨き粉より少し緩いくらいが目安)になるまで、プラスチックや木の棒でよくかき混ぜて完成です。
注意点:オキシペーストは作るとすぐに反応が始まり、効果が時間とともに薄れていきます。作り置きはせず、使う直前に必要な分だけ作るようにしてください。
オキシペーストの強力なメカニズム
このペーストがなぜ強力なのか? それは、両者の長所が組み合わさるからです。
- 重曹の「増粘・密着」効果:水に溶けにくい重曹がペーストの基剤(ベース)となり、液体では流れ落ちてしまうオキシクリーンを、壁面などの垂直な場所にしっかり「密着」させます。
- オキシクリーンの「漂白・分解力」:密着することで、活性酸素が汚れに長時間とどまり、じっくりとカビやシミを化学的に分解・漂白します。
- 重曹の「研磨力」:最後にこすり洗いをする際に、重曹の粒子が物理的な研磨力を加え、汚れを削り落とします。
つまり、「オキシクリーンの化学的な漂白力を、重曹の物理的な力で汚れに貼り付け、さらに研磨力も追加したもの」と言えますね。
これは、オキシクリーン単体(液体)でも、重曹単体(研磨)でも対応できない、頑固な汚れに対して非常に有効なテクニックです。
オキシクリーンと重曹の場所別掃除術

それでは、ここからは具体的なお掃除シーンを想定して、「オキシクリーンと重曹、どっちを使うべきか?」を、キッチン、洗濯槽、お風呂場といった場所別に詳しく見ていきましょう。理論が分かったところで、実践編ですね!
洗濯槽の掃除はオキシクリーン一択
まず、多くの人が悩む「洗濯槽の掃除」ですが、これはもう、議論の余地なくオキシクリーン(過炭酸ナトリウム)の一択です。
なぜ重曹がダメなのかというと、理由は3つあります。
- アルカリ度が低すぎる:洗濯槽の裏側に潜んでいるのは、溶け残った洗剤カスや柔軟剤、衣類からの皮脂汚れをエサにして繁殖した「黒カビ」の複合体(バイオフィルム)です。これらは非常に頑固で、重曹(pH 8)の弱いアルカリパワーでは全く歯が立ちません。
- 漂白力がない:重曹にはカビを殺菌したり漂白したりする効果はありません。
- 発泡力が弱い:汚れを「剥がし取る」力も期待できません。
一方、オキシクリーン(過炭酸ナトリウム)は、市販されている「酸素系洗濯槽クリーナー」の主成分そのものです。そのpH 11の強力なアルカリ性で皮脂汚れを分解し、活性酸素の強力な発泡力で、こびりついたカビを物理的に「バリバリッ」と剥がし取ります。
基本的な使い方(縦型洗濯機)
40℃~60℃のお湯を高水位まで溜め、オキシクリーン(日本版の場合、湯10Lあたり約100gが目安ですが製品の指示に従ってください)をしっかり溶かします。その後、「洗い」コースで数分間回して攪拌し、数時間(2~6時間)放置して「オキシ漬け」します。最後に浮いてきた汚れ(ワカメのようなピロピロ汚れ)を網ですくい取り、標準コースを1~2回運転して完了です。
ドラム式洗濯機の場合の注意点
ドラム式洗濯機は、構造上、縦型のように高水位まで水を溜める「オキシ漬け」ができません。また、機種によっては過炭酸ナトリウムの使用が禁止されている場合もあります。 ドラム式でオキシクリーンを使いたい場合は、必ずご使用の洗濯機の取扱説明書を確認し、「槽洗浄コース」での使用が可能か、分量はどうなっているかを確認してください。無理に使うと故障の原因にもなりかねないので、メーカー指定の専用クリーナー(塩素系が多いです)を使うのが最も安全かもしれませんね。
風呂場の黒カビ撃退法

お風呂場の壁のタイル目地や、ドアのゴムパッキンに発生した根深い黒カビ。これはオキシクリーンで漂白したいところですが、オキシ液(お湯で溶かしたもの)をスプレーしても、垂直な面なのですぐに流れ落ちてしまいますよね。
ここで活躍するのが、先ほどご紹介した「オキシペースト」です。
オキシペーストを使い古しの歯ブラシや綿棒などで、カビが発生している箇所に「塗り込む」ように塗布します。その際、ペーストが乾燥すると効果が落ちてしまうため、上からラップでパック(湿布)をするのが最大のコツです。
そのまま1時間ほど放置し、ラップを剥がしてからブラシでこすりながらお湯で洗い流せば、オキシクリーンの漂白力と重曹の研磨力のダブルパンチで、カビをかなり薄くできるはずです。根深いカビは何度か繰り返す必要があるかもしれません。
キッチンの排水溝掃除

キッチンの排水溝は、食材のカス、油汚れ、皮脂、石鹸カス、カビが混ざった「ぬめり汚れ」の巣窟です。臭いの元にもなりますよね。
ここも汚れのレベルによって使い分けるのがおすすめです。
月1回の徹底掃除:オキシクリーン
月に1回など、徹底的にリセットしたい場合は、オキシクリーンの「オキシ漬け」が効果的です。排水溝のフタやゴミ受け、トラップの部品など、外せるパーツをすべて外し、シンクにお湯(40℃~60℃)を溜めます(排水口はビニール袋に水を入れた「水栓」などで塞ぎます)。そこにオキシクリーンを溶かし、パーツ類ごと数時間漬けおきします。オキシクリーンの漂白・除菌作用で、ぬめりや臭いの元を分解してくれます。
日常的なケア:重曹
「そこまで汚れていないけど、最近ちょっと臭いが気になる」という日常的なケアであれば、安全性の高い重曹が手軽です。重曹を粉末のまま排水溝のゴミ受けやその周りに振りかけて、30分ほど放置します。その後、お湯(60℃程度)で一気に流すだけでも、軽いぬめり取りや消臭効果(酸性のニオイの中和)が期待できますよ。
頑固な焦げ付きを落とす研磨力

鍋やフライパン、コンロの五徳にこびりついた真っ黒な焦げ付き。これは油や食材が熱によって「炭化」した、非常に硬い汚れです。
漂白剤であるオキシクリーン(化学的アプローチ)では、この炭化した汚れを分解するのは非常に難しいです。こういう時こそ、重曹の出番です。重曹の「物理的な研磨力」が最も効果を発揮するシーンですね。
重曹に少量の水を加えて「重曹ペースト」(重曹2:水1くらいが目安)を作り、焦げ付きに塗り込んでしばらく放置します(30分~)。その後、丸めたアルミホイルや硬めのスポンジ、ステンレスたわしなどで円を描くようにこすると、重曹の粒子が研磨剤となり、焦げを「削り落とす」ことができます。
もちろん、オキシペーストを使えば漂白効果もプラスされますが、純粋な「焦げ(炭化)」に対しては、まずは重曹の研磨力を試すのがセオリーかなと思います。
テフロン加工(フッ素樹脂加工)のフライパンには、重曹ペーストもアルミホイルも絶対に使わないでください!研磨作用でコーティングが剥がれてしまいます。
使ってはいけない素材と注意点
オキシクリーンも重曹も非常に便利な洗浄剤ですが、万能ではありません。それぞれの特性(強アルカリ性、研磨性)ゆえに、使ってはいけない素材が存在します。これを間違えると、修復不可能なダメージを与えてしまう可能性があるので、ここはしっかり確認してください。
オキシクリーン(強アルカリ性)がNGな素材
- ウール、シルク、革製品:これらは動物性のタンパク質繊維です。強アルカリによって繊維が溶けたり、縮んだり、ごわごわになったりします。
- 金属全般:変色やサビの原因になることがあります。ステンレスは比較的強いですが、長時間の漬けおきは避けた方が無難です。
- 素手での使用:pH 11の強アルカリ性は、皮膚のタンパク質を溶かします(ぬるぬるするのは皮膚が溶けているサインです)。深刻な手荒れの原因になるため、必ずゴム手袋を着用してください。
- 密閉容器での保存・使用:オキシクリーンは酸素ガスを発生させ続けます。スプレーボトルなどで密閉すると内圧が上昇し、容器が破裂する危険があります。
重曹(研磨性)がNGな素材
- 大理石(天然・人工):研磨作用により、表面の美しい光沢が失われ、マットな質感になってしまいます。
- 畳、白木、ワックスがけされたフローリング:研磨作用により、表面が削れて白っぽくなったり、ワックスが剥がれたりします。
- 漆器、アクリル素材(お風呂の浴槽など):柔らかい素材は表面に微細な傷(スクラッチ傷)がつきます。
最重要禁忌:アルミニウム製品
そして、オキシクリーンと重曹に共通する、最も重大な禁忌事項が「アルミ製品への使用」です。
雪平鍋、パスタ鍋、やかん、フライパン、シンクの部品など、キッチン用品にはアルミが使われていることが多いです。
アルミニウムは、酸にもアルカリにも反応する「両性金属」と呼ばれる特殊な金属です。
オキシクリーン(強アルカリ性)および重曹(弱アルカリ性)のどちらの溶液も、アルミニウムの表面と化学反応を起こし、腐食させてしまいます。その結果、表面が真っ黒に変色(黒変)してしまうのです。この化学変化は不可逆的であり、一度黒変してしまったら、元のピカピカな状態に戻すことはほぼ不可能です。
「この鍋、素材は何だっけ?」と少しでも迷った時は、使用を避けるか、必ずメーカーの取扱説明書や製品表示(「アルマイト加工」なども注意)を確認するようにしてくださいね。
オキシクリーンと重曹の使いこなし術
ここまで見てきたように、オキシクリーンと重曹は、洗浄剤としての目的もメカニズムも、根本的に全く異なる物質であることがお分かりいただけたかなと思います。
「どちらが優れているか」という比較対象ではなく、それぞれが異なる武器を持った「全く異なる工具」なんですね。
大まかな役割分担を最後にもう一度おさらいすると、
- オキシクリーン(化学の力):pH 11の強アルカリ性&活性酸素の力で、汚れを「漬けて漂白・分解・剥離」する。
- 重曹(物理の力):pH 8の弱アルカリ性&水に溶けにくい粒子の力で、汚れを「こすって研磨・中和」する。
オキシクリーンと重曹、この2つの「違い」と「得意分野」をしっかり理解して、「適材適所」で使い分けること。それが、お掃除・お洗濯マスターへの一番の近道だと私は思います。
ぜひ、ご家庭の気になる汚れと見比べながら、「この汚れは色素沈着だからオキシクリーンだな」「この焦げ付きは重曹の研磨力が必要だな」と、2つのアイテムを使いこなしてみてくださいね!