ドラッグストアやホームセンターに行くと、本当にたくさんの種類があって迷ってしまいますよね。結局万能なのはどれ?最強の洗剤って何?と悩む方も多いかなと思います。私も昔は、CMでよく見るものや、パッケージが強力そうなものを選んでは「あれ、思ったより落ちないな…」と首をかしげることがよくありました。
キッチンでの頑固な油汚れ、浴室の水垢やカビ、トイレの黄ばみなど、場所別に専用洗剤を買うべきか、それともウタマロやオキシクリーンのような人気商品で全部できるのか。この悩み、とてもよく分かります。
実は洗剤選びで本当に大切なのは、ブランド名や価格ではなく、目の前の汚れの「種類」をしっかり理解することなんです。汚れには酸性やアルカリ性といった化学的な性質があり、その性質を知ることで、なぜその汚れにその洗剤が効くのかが理論的にわかってきます。これがわかると、重曹やクエン酸、セスキ炭酸ソーダといったナチュラルクリーニングも、単なる気休めではなく「化学兵器」として上手に使いこなせるようになりますよ。
この記事では、掃除洗剤を汚れ別、場所別にどう選ぶか、その化学的な基本から、私なりの実践的な使い方まで、分かりやすく丁寧に解説していきますね。
- 洗剤選びの失敗しない「化学」の基本
- 汚れの種類(酸性・アルカリ性)の見分け方
- 場所別(キッチン・浴室・トイレ)のおすすめ洗剤
- 重曹やクエン酸などの賢い使い分け
汚れが落ちるおすすめの掃除用洗剤はこれ!
本当に汚れが落ちる洗剤ってどれなの?
王道の洗剤からコアな洗剤まで、40種類の洗剤を紹介!
\ 最適な一本が見つかる! /
おすすめ掃除洗剤の前提は「汚れの化学」

洗剤選びって、つい強力そうとか人気だからで選んじゃいませんか?もちろん、それも一つの選び方ですが、もし掃除を効率的に、最短で終わらせたいと思うなら、知っておくべきは汚れと洗剤の相性なんです。この相性を決めるのが化学(pH)なんですね。ちょっと理科の授業みたいですが、ここが一番のキモなので、分かりやすく解説します。
汚れは酸性とアルカリ性の2種類
まず、家庭内の汚れは、大きく2つのタイプに分けられると覚えてください。これがわかれば、掃除の半分は終わったようなものです。
1. 酸性の汚れ(有機物・油分)
これらは主に、私たち人間や食べ物から出る汚れです。特徴は、ベタベタ、ネバネバ、ヌルヌルしていること。触るのがちょっとためらわれるような汚れが多いですね。
- キッチンのコンロ周りの油汚れ
- 換気扇に固着した茶色い油
- 床や壁についた手垢、足裏の皮脂汚れ
- 食べこぼしのシミ
- 浴槽の湯垢(皮脂が混ざったもの)
- タバコのヤニ
2. アルカリ性の汚れ(無機物・ミネラル)
これらは主に、水道水に含まれるミネラル分が固まった汚れです。特徴は、白っぽく、カリカリ、ガリガリ、ザラザラしていること。力任せにこすると傷がつきそうな、硬い汚れですね。
- お風呂の鏡や蛇口についた白い水垢(ウロコ汚れ)
- 浴室の壁や床に付着した石鹸カス(皮脂と水道水ミネラルが結合したもの)
- トイレの便器にこびりつく黄ばみ(尿石)
- 電気ポットや加湿器の内部につくカルキ汚れ
- シンクにできる白い輪ジミ
| 汚れの性質 | 特徴 | 主な具体例 |
|---|---|---|
| 酸性の汚れ | ベタベタ、ネバネバ、油っぽい | キッチンの油汚れ、皮脂汚れ、手垢、湯垢、食べこぼし |
| アルカリ性の汚れ | カリカリ、ザラザラ、白っぽい、硬い | 水垢、石鹸カス、尿石、カルキ、シンクの輪ジミ |
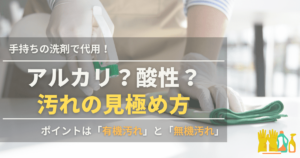
洗剤の基本は「中和」する使い分け

汚れのタイプがわかれば、掃除の答えは驚くほどシンプルです。それは「中和」して落とすこと。
学校の理科の実験で、リトマス試験紙を使ったのを思い出すかもしれませんが、まさにアレです。酸性のものとアルカリ性のものを混ぜると、お互いの性質を打ち消し合って「中性」に近づきます。この化学反応を利用して、汚れを素材から剥がしやすくするのが、掃除の基本的な考え方なんですね。
洗剤選びの絶対法則(中和のルール)
- ベタベタする「酸性の汚れ」には → 「アルカリ性の洗剤」を使う
- カリカリする「アルカリ性の汚れ」には → 「酸性の洗剤」を使う
例えば、お風呂の鏡についたカリカリの水垢(アルカリ性)を、同じアルカリ性の洗剤(カビキラーなど)で一生懸命こすっても、化学的には中和されないので、ほとんど効果がありません。逆もまた然りで、キッチンの油汚れ(酸性)に、クエン酸(酸性)をスプレーしても、汚れはまったく落ちないんです。
「この洗剤、洗浄力が弱いな…」と感じる原因の多くは、実は洗剤のパワー不足ではなく、このpHの組み合わせが根本的に間違っているだけ、ということが多いんですよ。
ウタマロなど中性洗剤の得意な汚れ

「じゃあ、いつも使っている食器用洗剤やウタマロクリーナーのような中性洗剤は?」と思いますよね。「万能」と紹介されることも多いですが、これにも得意・不得意があります。
中性洗剤(pH6〜8)は、酸性やアルカリ性の洗剤のように、汚れを化学的に「中和」して分解する力は強くありません。中性洗剤の主な洗浄力は、「界面活性剤」という成分によるものです。この成分が、水と油のように混じり合わないものの境界線(界面)に働いて、汚れを浮かせて包み込み、素材から剥がし取るイメージですね。
代表的なのはウタマロクリーナーや、環境配慮型洗剤として人気の「緑の魔女」などです。
中性洗剤のメリット
最大のメリットは、素材へのダメージが最も少ないことです。pHが中性なので、酸性洗剤のように金属をサビさせたり、アルカリ性洗剤のようにワックスを剥がしたりするリスクが低いんです。だから、リビングの床(フローリング)、塗装された家具、壁紙、食器洗いなど、デリケートな場所や日常的な軽い汚れ(ホコリや軽い皮脂)を落とすのに向いています。
中性洗剤の限界
逆に、デメリットは、化学的な中和を必要とする頑固な汚れには力不足なことです。長期間放置されて固着した水垢(アルカリ性)や、ギトギトに固まった油汚れ(酸性)を、中性洗剤だけで落とすのはかなり難しいですね。
私の使い方としては、まず中性洗剤で試してみて、それで落ちなければ「あ、これは中和が必要な頑固な汚れだな」と「診断」する、という使い方がおすすめです。
油汚れにアビリティクリーンを使う
キッチンのコンロのギトギト、換気扇のベタベタ、壁の手垢、浴槽の湯垢。これらはすべて「酸性の汚れ」です。
こういう汚れには、アルカリ性(または弱アルカリ性)の洗剤を使いましょう。アルカリ性が油(酸性)と化学反応を起こし、これを分解(専門用語で「鹸化(けんか)」と言います)して、水に溶けやすい物質に変えてくれるんです。
アルカリ性洗剤の種類と強さ
アルカリ性洗剤にも強さのレベルがあります。
- 弱アルカリ性 (pH 8超〜11以下): 重曹、セスキ炭酸ソーダ、過炭酸ナトリウム(オキシクリーン)、超電水クリーンシュ!シュ!(アルカリ電解水)など。 比較的マイルドですが、日常的な皮脂汚れや軽い油汚れなら十分対応できます。特にセスキ炭酸ソーダは水に溶けやすくスプレーにしやすいので、壁の手垢などに便利です。
- アルカリ性 (pH 11超): アビリティクリーン、ウルトラハードクリーナー(油汚れ用)、キッチンマジックリン、換気扇専用クリーナー(例:なまはげ)など。 非常に強力で、頑固に固まった油汚れや焦げ付きに効果を発揮します。その分、素材や肌へのダメージも強力です。
アビリティクリーンは、ヤシの実由来の界面活性剤を使った強力なアルカリ性洗剤で、プロの現場でも使われることがあるほどです。油汚れへの浸透力が高いのが特徴ですね。
使用上の注意点
アルカリ性はタンパク質(つまり私たちの皮膚)を溶かす性質があります。pHが高い洗剤を使う場合は、必ずゴム手袋を着用してください。素手で触ると、皮膚がヌルヌルしてきますが、それは皮脂が溶けているサインです。
また、アルミ製品(鍋、フライパン、換気扇のフィルターなど)や、銅製品は黒く変色してしまうため、使用は避けてくださいね。フローリングのワックスを剥がしてしまう可能性もあります。
水垢・尿石は茂木和哉や酸性洗剤で

お風呂の鏡の白いウロコ汚れ、蛇口のカリカリ、シンクの白い輪ジミ、トイレの便器の黄ばみ(尿石)。これらは水道水中のミネラル(炭酸カルシウムなど)が固まった、しつこい「アルカリ性の汚れ」です。
このタイプの汚れは、物理的にこすり落とそうとしてもなかなか取れません。酸性(または弱酸性)の洗剤を使って、化学的に中和し、溶かして落とすのが正解です。
酸性洗剤の種類と強さ
- 弱酸性 (pH 3以上〜6未満): クエン酸、お酢など。ナチュラルクリーニングで人気ですね。日常的な水垢や石鹸カス、電気ポットのカルキ汚れなら、これで十分対応できます。
- 酸性 (pH 3未満): トイレ用洗剤(サンポールなど)、茂木和哉 水アカり、ウルトラハードクリーナー(ウロコ・水アカ用)など。 非常に強力で、長年蓄積してカチカチになった尿石や、何をしても取れなかった鏡のウロコ汚れに効果的です。ただし、取り扱いには細心の注意が必要です。
特に「茂木和哉」シリーズは、温泉の水垢と戦ってきた知見から生まれた洗剤で、プロも使うほど強力な酸性洗剤です。諦めていた水垢に最終兵器として使う人も多いですね。
使用上の注意点
酸性洗剤も皮膚への刺激が強いので、ゴム手袋の着用をおすすめします。また、鉄などの金属に使うとサビの原因になったり、コンクリートや天然の大理石(人造大理石含む)に使うと、表面のツヤが溶けて失われたりするので、使用は厳禁です。浴室やキッチンのカウンターの素材は事前に必ず確認してください。
重曹・セスキ・クエン酸の使い分け

最近人気の「ナチュラルクリーニング」も、結局は化学です。「環境にやさしい」というイメージがありますが、これらも立派な化学物質。それぞれに得意・不得意がはっきりしています。
特に「重曹とクエン酸を混ぜて使う」という方法を見かけますが、アルカリ性と酸性を混ぜると中和してしまい、お互いの洗浄力を打ち消しあってしまいます(発泡する力で汚れを浮かせる目的もありますが…)。基本は単体で、汚れのpHに合わせて使い分けるのがおすすめです。
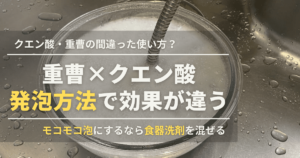
| 洗剤名 | 液性 | 得意な汚れ(中和対象) | 特徴・主な用途 |
|---|---|---|---|
| クエン酸 | 酸性 | アルカリ性汚れ(水垢、石鹸カス、尿石) | 水に溶かしてスプレーにし、シンクや浴室、トイレの掃除に。 |
| 重曹 | 弱アルカリ性 | 酸性汚れ(軽い油汚れ、皮脂) | 粒子が細かく水に溶けにくいため「研磨力」が強い。鍋の焦げ付き磨きに。 |
| セスキ炭酸ソーダ | アルカリ性 | 酸性汚れ(油汚れ、皮脂、手垢) | 重曹よりアルカリ性が強く水に溶けやすい。スプレーや「つけおき」で油汚れに。 |
| 過炭酸ナトリウム | 弱アルカリ性 | 酸性汚れ(皮脂、黄ばみ)、色素汚れ | オキシクリーンの主成分。お湯で「酸化力」が発生。漂白・除菌・消臭に。 |
重曹(JUSO / 弱アルカリ性)
アルカリ性洗剤としては非常にマイルドです。最大の特徴は、水に溶けにくい粒子による「研磨力」。水と混ぜてペースト状にし、クレンザーのようにして鍋の焦げ付きや五徳の汚れを、こすり洗いするのに最適です。頑固な油汚れを分解する力はセスキ炭酸ソーダに劣ります。
セスキ炭酸ソーダ(Sesqui / アルカリ性)
重曹よりもアルカリ性が強く(重曹の約10倍とも言われます)、水によく溶けます。研磨力はありません。油汚れやタンパク質汚れ(皮脂、血液)を強力に分解するので、水に溶かしてスプレーボトルに入れ、壁やドアノブの手垢を拭いたり、お湯に溶かして換気扇のファンを「つけおき」したりするのに向いています。
クエン酸(Citric Acid / 酸性)
ナチュラルクリーニングにおける酸性担当です。水に溶かして「クエン酸スプレー」を作っておくと、シンク、浴室、鏡、グラスの水垢、トイレの黄ばみやニオイ消し(アンモニアはアルカリ性なので)に大活躍します。ただし、カビを殺菌する力はほぼありません。
過炭酸ナトリウム(酸素系漂白剤 / 弱アルカリ性)
これは「オキシクリーン」の主成分として有名ですね。厳密には「洗剤」というより、お湯(40〜60℃)と反応して酸素の泡を出し、その酸化力で汚れを「漂白・除菌・消臭」するものです。塩素系漂白剤と違って色柄物にも使えますが、あくまで「漂白剤」なので、素材によっては色落ちすることもありますし、素手での使用は厳禁です。
オキシクリーン(過炭酸ナトリウム)は、酸性の皮脂汚れや黄ばみを落とすのは得意ですが、水垢(アルカリ性)を落とす力はほぼありません。pH(弱アルカリ性)と酸化力(漂白)の両面で汚れを落とす、週末用のスペシャルケアアイテムと考えるのが良いですね。
こうしたナチュラル洗剤の使い分けについては、当サイトの別記事でも、さらに詳しく紹介していますよ。それぞれを使いこなせると、掃除のレベルが格段に上がります。

場所別!おすすめ掃除洗剤と最強の掃除術

理屈がわかったところで、次は実践編です。「じゃあ、うちのキッチンには結局どれ?」となりますよね。キッチン、浴室、トイレなど、場所ごとにどんな汚れが多くて、どの洗剤を使えば効率的か、私のやり方も含めて紹介しますね。
キッチン掃除:ウルトラハードと茂木和哉
キッチンは「酸性の油汚れ」と「アルカリ性の水垢」が混在する、最も化学的な使い分けが必要な場所です。ここで使い分けができれば、もう上級者ですね。
コンロ・換気扇・グリル
ここはもちろん「酸性の油汚れ」の巣窟です。料理で飛び散った油や、それがホコリと混じって固まった汚れですね。
推奨洗剤:アルカリ性洗剤(リンレイ ウルトラハードクリーナー 油汚れ用、アビリティクリーン、セスキ炭酸ソーダなど)
日常的なコンロ周りの拭き掃除なら、セスキ炭酸ソーダスプレーで十分です。数ヶ月放置したような頑固な油汚れや換気扇のフィルター、グリルの部品などは、ウルトラハードクリーナーやなまはげのようなプロ仕様に近い強力なアルカリ性洗剤を使うのが近道です。取り外せる部品は「つけおき」するのが一番ラクで、効果的です。この時、アルミ製のフィルターは変色するのでアルカリ性洗剤を使わないよう注意してくださいね。
シンク・蛇口
ここは「アルカリ性の水垢」がメイン。水道水が蒸発した後に残る、白いウロコ状のカリカリ汚れです。
推奨洗剤:酸性洗剤(茂木和哉、クエン酸など)
軽い水垢ならクエン酸スプレーで十分です。それでも落ちない頑固な水垢には、キッチンペーパーにクエン酸スプレーを浸し、汚れに貼り付けてパックする「クエン酸パック」を試してみてください。それでもダメなら、最終兵器として「茂木和哉」のような研磨剤も配合された強力な酸性洗剤の出番です。これで驚くほどキレイになりますよ。
浴室掃除:カビキラーとオキシクリーン

お風呂は家庭内で一番やっかいかもしれません。なぜなら、「酸性の皮脂汚れ(湯垢)」、「アルカリ性の水垢・石鹸カス」、そして「生物由来のカビ」の3種類の主要な汚れがすべて発生するからです。
これを1本の中性洗剤(バスマジックリンなど)だけで全部落とそうとするから失敗するんですね。浴室掃除は、汚れの種類別に「洗剤を変える」のが鉄則です。
ステップ1:酸性汚れ(皮脂・湯垢)の除去
浴槽のフチや、洗い場の床がザラザラ・ヌルヌルする原因は、私たちの体から出た「皮脂汚れ」です。これは酸性なので、中性洗剤(バスマジックリンなど)か、より強力に落とすなら弱アルカリ性の洗剤(オキシクリーンで床をこする「オキシこすり」など)で落とします。オキシクリーンは皮脂汚れに強く、除菌・消臭効果も期待できるので、浴室全体の掃除に便利ですね。
ステップ2:アルカリ性汚れ(水垢・石鹸カス)の除去
鏡のウロコ、蛇口の白いカリカリ、浴室の壁や棚に付着した白い汚れ。これは「水垢」や、皮脂と水道水ミネラルが結合した「石鹸カス」で、アルカリ性です。ステップ1の洗剤では落ちません。
茂木和哉やウルトラハードクリーナー(ウロコ・水アカ用)、またはクエン酸を使って、中和して落とします。鏡のウロコには、茂木和哉のような研磨剤入りが特に効果的です。
ステップ3:生物由来汚れ(カビ・ピンク汚れ)の除去
ゴムパッキンやタイルの目地に発生した黒カビ、床の隅に出るピンク汚れ(ロドトルラという酵母菌)。これらは中和では落ちません。生物なので、殺菌が必要です。
塩素系漂白剤(カビキラーなど)をピンポイントで使って、殺菌・漂白します。液だれしやすい壁面には、ジェルタイプのカビ取り剤(茂木和哉 カビとりジェルスプレーなど)もおすすめです。
トイレの黄ばみはサンポールで

トイレの嫌なニオイや、便器にこびりつく黄ばみの原因は、主に尿が変化して固まった「アルカリ性」の尿石です。ニオイの元であるアンモニアもアルカリ性ですね。
便器の内部
推奨洗剤:酸性洗剤(サンポール、茂木和哉 尿石用など)
フチ裏の頑固な黄ばみ(尿石)には、サンポールのような強力な酸性洗剤が最も効果的です。洗剤をかけて、トイレットペーパーでパックし、30分ほど放置してからブラシでこすると、硬い尿石が中和されて落としやすくなります。それでも落ちない場合は、尿石専用の「茂木和哉 尿石用」などを試してみるのも良いと思います。
壁・床の拭き掃除
推奨洗剤:クエン酸スプレー、超電水クリーンシュ!シュ!
目に見えなくても、壁や床には尿が飛び散っています。ニオイ対策には、アルカリ性を中和するクエン酸スプレーでの拭き掃除が効果的です。また、除菌も兼ねるなら、アルカリ電解水の「超電水クリーンシュ!シュ!」のような、二度拭き不要のクリーナーも便利ですよ。
リビングや床は緑の魔女・ウタマロ

リビングや床の汚れは、主にホコリと、足裏の皮脂や壁の手垢といった比較的軽度な「酸性」の汚れです。
「じゃあアルカリ性洗剤(セスキ炭酸ソーダなど)?」と思いがちですが、ちょっと待ってください。フローリングのワックスや繊細な壁紙は、アルカリ性洗剤でダメージを受けてしまう可能性があります。ワックスが剥がれたり、壁紙が変色したりしたら大変ですよね。
こういうデリケートな場所は、まず中性洗剤から試すのが鉄則です。特に「ウタマロクリーナー」は、中性でありながら皮脂汚れに強く、2度拭きも不要なので、リビング周りの掃除には本当に使いやすいですね。
また、床掃除には「緑の魔女 キッチン」もおすすめです。こちらも中性で素材に優しく、バイオの力で排水パイプもキレイにしてくれるという特徴があります。
「緑の魔女」は、使用後の排水が自然界の微生物の働きを助け、パイプの汚れを分解する「バイオ・パイプクリーニング」という発想の洗剤です。環境への配慮を重視する方には特におすすめですね。
中性洗剤を使う時の注意点
中性洗剤とはいえ、界面活性剤は含まれています。フローリングのワックスの種類によっては、相性が悪い場合もあるかもしれません。初めて使う場所では、必ず目立たない隅の方で試してから全体に使うようにしてください。
混ぜるな危険!カビキラーと酸性洗剤

ここまで色々な洗剤を紹介してきましたが、最後に一番大事な「安全」の話をさせてください。掃除は家をキレイにするためのものですが、使い方を間違えると、健康を害したり、最悪の場合、命に関わる事故につながる可能性があります。
洗剤は、汚れを落とすための強力な「化学薬品」である、という意識を常に持っていてください。
【最重要】絶対に混ぜないでください!
「塩素系」洗剤 と 「酸性タイプ」洗剤
これは、もう理屈抜きで絶対に覚えてください。この2つが混zると、人体に極めて有毒な「塩素ガス」が発生します。実際に、掃除中にこのガスを吸い込んで中毒を起こし、病院に運ばれたり、亡くなったりする事故が毎年発生しています。
- 【塩素系】の代表例:カビキラー、カビハイター、キッチンハイター、パイプユニッシュ、トイレハイター、ドメスト など
- 【酸性タイプ】の代表例:クエン酸、サンポール、茂木和哉 水アカり、お酢、水垢・ウロコ取り専用洗剤 など
ボトルの中で混ぜるだけでなく、同じ場所で続けて使うのも「混合」にあたります。(例:お風呂でカビキラー(塩素系)を使った直後に、水垢に茂木和哉(酸性)をかける、など)絶対にやめてください。
安全に掃除するための基本ルール
事故を防ぎ、安全に掃除を行うため、以下のルールを必ず守ってください。
- 1. 必ず換気する 塩素系はもちろん、酸性や強アルカリ性の洗剤を使う時は、必ず窓を2ヶ所以上開けるか、換気扇を「強」で回し、空気の流れを作ってください。
- 2. 必ず保護する(手袋・マスク) アルカリ性は皮膚(タンパク質)を溶かし、酸性は金属や皮膚を腐食させます。ゴム手袋の着用は義務だと思ってください。オキシクリーンやセスキ炭酸ソーダなども素手はNGです。ニオイが強いものはマスクも着用しましょう。
- 3. 必ずラベルを読む 使用前に必ず洗剤の裏面の「液性(酸性、中性、アルカリ性)」と「使えない素材」を確認してください。「大理石NG(酸性)」「アルミNG(アルカリ性)」など、建材との相性を守ることが不可欠です。
- 4. 弱いものから試す 汚れを落としたい一心で、いきなり最強の洗剤を使うのはやめましょう。素材を傷めたら元も子もありません。必ず「中性洗剤」から試し、落ちなければ「弱アルカリ性・弱酸性」、それでもダメなら「アルカリ性・酸性」と、徐々に強くしていくのが鉄則です。
これらの情報はあくまで一般的な目安です。ご自身の健康状態や、ご自宅の建材(特に高価なもの)に不安がある場合は、使用を控えるか、ハウスクリーニングの専門業者にご相談くださいね。

最適な「おすすめ掃除洗剤」の見つけ方
ここまでお読みいただき、本当にありがとうございます。
結局のところ、「最強の万能洗剤」を1本探すよりも、目の前の汚れが「酸性か、アルカリ性か」を考えるクセをつけることが、掃除上級者への一番の近道だと私は思います。これが「汚れを診断する」ということです。
汚れを診断できれば、ドラッグストアの棚の前で迷うことはありません。「キッチンの油汚れ用だから、アルカリ性のアビリティクリーンにしよう」「お風呂の鏡のウロコだから、酸性の茂木和哉だ」と、論理的に「解」を選べるようになります。
この記事を参考に、ご自宅の汚れと場所に合わせて、最適な「おすすめ掃除洗剤」のスタメンを見つけてみてください。
まずは安全な中性洗剤を基本に、落ちない汚れが出てきたら「これは油汚れだからアルカリ性だな」「これは水垢だから酸性だな」と、化学の力でスマートに解決する。ぜひ試してみてくださいね。
\ 当サイトで紹介しているその他の洗剤はこちら /





















